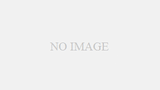慢性的な腰痛や肩こりの原因
症状がなかなか良くならない慢性的な腰痛・肩こりの原因に対して、一般的に整体では、
・骨格の歪みや筋肉疲労
をあげることが多いです。
当院でも初診のお客様には、その改善の為に姿勢不良の悪影響や改善方法を説明することが多いです。
ですが、腰痛・肩こりの原因は、他にもいくつかあります。
来院された時に、時間の都合上説明しきれない為、補足します。
多くの原因があり、読むだけでも大変かもしれません。
※原因ではなく、ケアする方法を知りたい方はコチラからお読みください。
また、自己改善が苦手な人は、定期的な整体の利用を勧めます。
そのような方の為に整体はあります。
コリとは
腰痛や肩コリの原因を説明する前に、この症状で痛みを感じる理由を最初に説明したいと思います。
疲労から起こる一般的な腰痛や肩コリで痛みを感じる一番の理由は、筋肉のコリです。
そのコリとは、筋肉が収縮した状態が続いていることです。
コリで痛みを感じる理由
コリで痛みを感じる理由は
・炎症を起こした筋肉が収縮することでの痛み。
・収縮した筋肉が伸ばされることでの痛み。
があります。
このようなコリは、横になって眠る姿勢をとると痛みがなくなるのは、これらが理由にあります。
眠る姿勢では、脱力し、筋肉が収縮することも伸張することも少なくなります。
ただ、コリが強かったり、痛覚過敏になっていると寝返りするだけでも痛みを感じることがあります。
コリが作られる理由など詳しくは、コチラで書いています。
根本的な5つの原因
私たちの普段の生活には健康を害することがたくさん潜んでいます。
そして気づかない内にそれらが積み重なって症状は進行していきます。
その原因は、5つ考えられます。
①日常生活での不良。
②生活環境の不良。
③運動不足。
④個人の体質。回復力が低い。
⑤心理的なもの。脳のエラー
そして、これらが原因になり
A:血行不良。
B:筋疲労や神経圧迫。
が起こり、腰痛や肩コリが表れます。
そして、痛みの原因となっているものは、個人で違います。
この中の一つが大きな原因の場合もあれば、複数が原因の場合もあります。
整体を受けても元に戻る人は、これらのどれかが原因となっています。
ですが、人によっては様々な理由があり、これらを改善できないことがあります。
整体は、そのような方に定期的に活用いただく事で、生活の助けになればと思っております。
整体の役割
※整体は、手技療法の技術を用いて、AとBを改善させて症状のある部位を回復させる技術です。
A:血行不良。
B:筋疲労や神経圧迫。
また、当院では、その原因に気づいて頂く、原因を取り除く行動をとれるように促すことも大切だと思っております。
このような記事も、そのひとつです。
①日常生活での不良。
日常生活での不良は、
①姿勢不良
②乱れた食生活
③体の使い方
があります。
姿勢不良
姿勢は、仕事中の姿勢や家でくつろいでいる時の姿勢、睡眠時、運転時などがあります。
家でくつろいでいる時やテレビやスマホを見ている時の姿勢は、だいたい悪い姿勢です。
悪い姿勢とは、骨格や関節、筋肉に負担をかけ歪みを作る姿勢で、簡単な言葉で言えば猫背です。
そもそも睡眠時の姿勢を除き、くつろぐという姿勢はリラックス効果はありますが、良い姿勢とは言えません。
悪い姿勢について、下記リンク先ページに書いています。
ただ、このような姿勢をしてそれが痛みにつながる人、繋がらない人がいます。
痛みが出にくい人は、
・痛みの閾値が低い人。
・腹圧が強い人。
・痛みに対して恐怖心が少ない。
・体にプラスな事とマイナスな事の差し引きでプラスが強い。
このようなことが関係しています。
それぞれ他で書いてありますので、お読みください。
・痛みの閾値とはコチラ。
・腹圧についてはコチラ。
・足し算引き算についてはコチラ。
良い姿勢とは
良い姿勢とは、筋疲労が起きにくい、椎間板や関節に負担の少ない姿勢の事です。
その姿勢は、立位や座位でも同じく、頭の重心が体幹の重心とそろっている姿勢です。
外見では、姿勢を横から見ると、耳の穴と肩の中心が近い姿勢です。
そして、生理的湾曲をキープしている事も大事です。
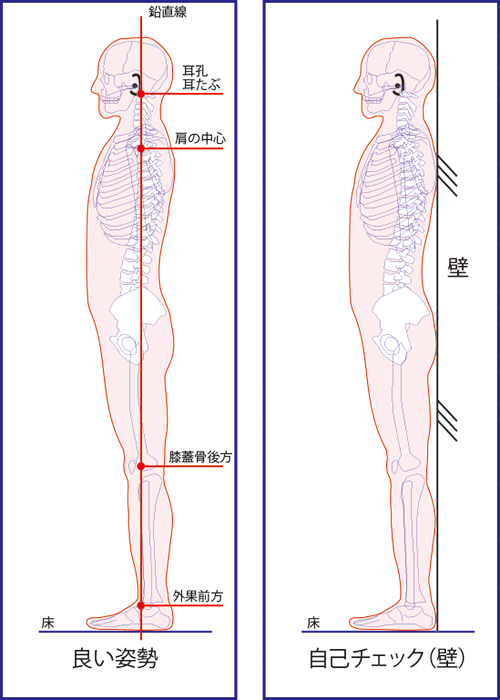
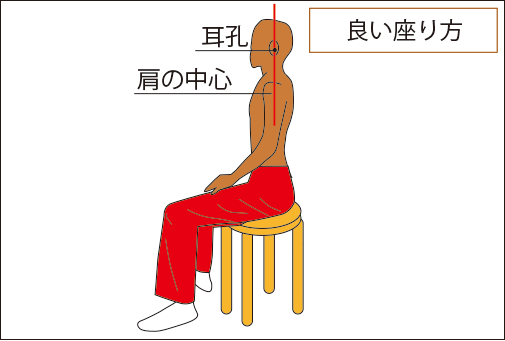
立位や座位での良い姿勢や自己チェック法について、以下のぺージを参照ください。
睡眠時の姿勢
睡眠は1日のうち3分の1~4分の1ほどの時間を費やしますが、体に合わない寝具を使っていれば、それだけ体に負荷をかけることになります。
眠っている間は、
・寝返りができている。
・睡眠の質が高い。
・うつ伏せ寝をしない。
この3点が大切です。
また、睡眠の質を高める方法の一つに、背骨の柔軟性に合った寝具選びも大切です。
よい睡眠の為にできることは、以下のページに書いてあります。
良くない食生活
良くない食生活は、
・血管にダメージを与える食べ方。
・食べ過ぎによる肥満。
があります。
肥満
肥満は、体に脂肪が増えることですが、脂肪には血液循環の補助をするミルキングアクションの作用がありません。
ミルキングアクションとは、筋肉が圧迫と弛緩を繰り返すことで静脈血を心臓に戻す働きのことを言います。
筋肉の間を通る血管は、この恩恵を得られますが、脂肪では得られません。
その為、体脂肪が多いと血液循環に悪影響を及ぼします。
血液の循環が悪ければ、痛みを感じる成分が停滞しがちで痛みを感じやすくなります。
血管にダメージを与える食事
血管にダメージを与える食事には、
・血糖を高める食事
・塩分の過剰摂取
高血糖
普段食べる白米や食パンは、GI値が高く、血管へのダメージが懸念される食べ物の一つです。
GI値とは、食品に含まれる糖質の吸収度合いを示す数値です。
高血糖が続くと酸化ストレスの増加して血管にダメージを与えます。
また、GI値は食材により異なります。
普段口にする食べ物には、食パンや白米があります。
血管や血液は、栄養や老廃物の運搬に必要なものです。
そこにダメージが加わると血管が硬くなったり、血管壁に脂肪が付着します。
そして血管や血液の質が低くなるとその分、体調に悪影響がでてきます。
塩分の過剰摂取。
塩分の過剰摂取は、
・高血圧
・むくみ
になる、リスクが高まります。
また、心臓や腎臓に負担が大きくなり、その病気になるリスクを高めます。
ただ、あくまで過剰摂取であって、摂らなさすぎも問題がありますが、通常、食事に意識していなければ過剰摂取の傾向にある為、注意が必要です。
むくみについては、整体で聞かれることが多いため、詳しくコチラ(当院別サイト)で書いています。
その他
食事以外では
・タバコ(百害あって一利なりと言われるほどのものです。)
・過剰飲酒(一日一合が適量と言われています。)
日常動作による影響。
日常生活による影響は、
・筋肉量や柔軟性
・呼吸の仕方や腹圧
があります。
筋肉量や柔軟性
筋肉量の減少は、運動不足や筋肉のつきやすさと関連するホルモンの減少が関係しています。
そして筋肉が少なくなると、骨格を支える為に筋肉は硬くなり、関節の可動域は狭くなりがちです。
例えば、股関節を動かす筋肉が細くなった場合。
股関節の筋肉が硬くなり可動域は減少し、歩幅を大きくとる為には腰椎や骨盤の動きが大きくなります。
そして、その分、腰回りの筋肉は疲労し、疲労が貯まれば痛みはでやすくなります。
ホルモンの影響
ホルモンとは、体内で分泌されますが、体の働きに作用します。
筋肉の成長に関係するホルモンには、
・テストステロン(男性ホルモン)
・成長ホルモン
があります。
このホルモンの減少には、運動不足と加齢が関係しています。
その為、女性は男性ホルモンが少なく筋肉がつきにくいのはその為です。
また、生まれつきの体質により、このホルモンが多い人と少ない人もいます。
また、筋肉を増やすには、筋肉への高負荷と栄養面でタンパク質が必要です。
そして歩くだけでは、歩くことに必要な筋肉しかつきません。
歩幅の小さい人は、その分の筋肉しかつきません。
動かさない部分の筋肉は、何もしなければ減少します。
また、筋肉が多くても股関節周りの柔軟性が少ない人は、同じ影響を受けます。
筋肉量だけではなく柔軟性も必要です。
当院では、これを考慮し腰痛持ちの方には、筋肉を緩めるだけではなく股関節周りの柔軟性を確保する整体を行っています。
呼吸や腹圧
普段、何気に行っている呼吸ですが、その呼吸で
・腹圧をかける筋肉が弱い。
・腹圧をかけれていない。
このような状態だと体幹を支える為に背部の筋肉に頼り、背中側の症状がでやすくなります。
つまり、背筋を使いすぎて背部にある腰や肩の筋肉が疲労し、腰痛や肩コリに繋がってしまいます。
このような状況に猫背が加算されるとさらに症状は辛くなります。
呼吸法や腹圧について、以下のリンク先のページに詳しく書いています。
②生活環境の不良
ここでの生活環境の不良とは、猫背を強いられる環境という意味です。
その環境は、普段の仕事や家事、育児をする上で避けることが難しいのが現状です。
これらの環境不良や姿勢不良により歪みは作られますが、単純に姿勢不良による筋疲労とその歪みを自ら補正しようとする平衡維持機能による筋疲労が長く続くと筋弛緩不全をが起こりコリが生じていきます。
また、姿勢を正そうと意識していも、避けられないことが多い為、どうしても背部の筋疲労や骨格の歪みは作られてしまう環境にあります。
筋弛緩不全
筋弛緩不全とは、筋肉が緩みにくくなるというものです。
筋肉が緩むには、筋肉を緩めるための伝達物質が筋肉に届く必要があります。
そして、なんらかの理由でその物質が届きにくくなると筋肉は硬くなってしまいます。
参考:関節可動域制限治療を考える(外部サイト)
栄養が届きにくくなる理由
筋肉への栄養や老廃物の運搬を行っている血管やリンパ管は、筋肉の間を通ります。
筋肉が使用されて収縮すると筋肉は硬く太くなりますが、それが長く続くとそれだけ循環が妨げられます。
このような筋肉が長期間使用されるケースは、平衡維持機能や姿勢を保つ姿勢があります。
そして、これは負のループになりやすいです。
負のループ:筋疲労で筋肉が硬くなる。 → 血管を圧迫 → 筋肉がさらに硬くなる。
平衡維持の為の筋収縮
人は立位や座位で両目を開いている間は、両目を水平に保とうとします。
これは平衡感覚を得るための働きによる作用です。
平衡感覚を得る情報はこれだけではありませんが、それを失うとめまいが起きやすくなります。
このような状態が続くと嘔吐中枢が刺激され気分が悪くなります。
つまり骨盤のや背骨の歪み、脚長差があれば、両目の水平は崩されますが、それを補うために頭を傾けたり、骨格を歪めてそれを補正しようとしています。
このような補正は、筋肉の働きで行われるために、その働きをする為の筋肉は、立位や座位では働き続ける為に疲労します。
それが先ほどの筋収縮不全に繋がりコリが作られてしまいます。
仕事の例
仕事といっても、多くありますが、大きく分けて
・デスクワーク
・体を使う仕事
があります。
デスクワーク
デスクワークでは、筆記やパソコンの操作があります。
筆記の際には、椅子に座り机の上に紙を置いて、それに字を書くと思います。
その際、用紙は机の上にあり、顔が下向きになります。
顔だけ下を向くと喉に圧迫がかかる為、背中を曲げてそれに対応し、猫背となります。
下を向いて字を書くことはできなくもないですが、作業効率が下がったり、集中しにくくなります。
パソコンの作業も同じく、ディズプレイ画面の中心は、座った時の目の高さより低い位置にあることが多いです。
その為、頭を前に傾ける動作と連動して背中が丸まりやすく猫背になります。
ノートパソコンは、デスクトップパソコンよりディスプレイが下になる為、さらに猫背を強めます。
ディスプレイの中心を目の高さと同じにすることで改善しやすくなりますが、会社の都合でそれはできないかもしれません。
また、座る時間が長いとお尻や太ももを圧迫する時間が長くなり、脚への血流が低下し座骨神経痛のリスクを高めます。
それと同じ姿勢が長ければ、肩や腰を動かす事が少なく血が停滞しがちとなり、腰痛や肩コリが起きやすくなります。
事務作業をされている方は、このような理由により腰痛や肩コリが起きやすくなります。
作業姿勢を改善できれば良いですが、なかなかそうはいかないのが現状ではないでしょうか?
家事
家事は、掃除や料理、育児があります。
これら全てにおいて、下を向くことが多いです。
育児は、小さい子供を相手にするため、目線を合わすために猫背になります。
また、子供を抱っこをしている時は、さらに腕に疲労が重なります。
抱っこを椅子に座って出来れば良いですが、なぜか子供がそれでは泣き止まないこともあり、がんばって抱っこするしかありません。
そして腕の筋肉まで硬くなれば、連結する肩の筋肉まで引っ張る為、さらに肩こりが増長します。
それに加え、猫背の姿勢で子供を抱っこするので腰の筋肉が疲労し、腰痛も起きます。
また、これらの高負荷は長期間続くため、首や腰の椎間板にダメージを与え、ヘルニアのリスクが高まります。
さらに出産間もない時期は、骨盤が次第に固定されていきますが、猫背をする時間が長い為、歪みをキープしたまま固定されてしまい、出産後から体調が変化する要因になります。
掃除も同じく、床に目を向けることが多いため、猫背になっています。
料理も同じく、調理台が低く設計されていることが多いため、猫背を強いられます。
このように子供を育てている時期は、子供から目が離せないことも多いため、運動する時間や自分の時間をとれない事も多いため、特に整体の利用を勧めます。
体を動かす仕事
仕事によっては、猫背や中腰が強いられます。
また、効率が重要視される為、姿勢をよくして効率が落ちれば、そうできないのがほとんどです。
看護、介護、保育、建築、運搬などは
・下を向く作業。
・人や荷物を移動させる仕事。
となり、猫背の状態で重いもの動かす事が多いため、腰への負担が大きくなります。
また、重いものを持つと腕は疲労するため、連結する肩の筋肉が引っ張られ、肩の痛みを感じやすくなります。
そして、中腰での作業は、腰への負荷が増大し、ヘルニアのリスクを高めます。
車の運転
車を運転するには、足でブレーキとアクセルを踏まなくてはいけません。
その為に膝を伸ばすことになります。
このような姿勢をするとハムストリングスという太ももの裏にある筋肉が引っ張られるため、その筋肉が着く骨盤が後方回転し、腰が後ろに曲がり、姿勢を正すことが簡単ではありません。
また、車の座席も衝突から身体を保護する為なのかわかりませんが、猫背になりやすい形状になっています。
この運転を生業とする職業は、長時間猫背が強いられるのと、体を動かす事がすくない為に腰痛や肩コリが起きやすくなります。
また、運転の仕事ではなくても、毎日片道に30分以上かかる通勤などは、そのリスクが高いと言えます。
運転の仕事は、それが仕事であり、職業病と言ってしまえばそれまでですが、それを補う何かをしなければ、時間経過と共に簡単には治りにくくなるので、注意が必要です。
立ち仕事
一見、立っているだけで動かないので楽そうに見えますが、長時間動かないことが体に負担をかけます。
動かなければ、筋肉の働きによる血流の補助作用が得ることができず、体がみくみやすくなります。
そしてそれを1日中続ければ、立つたまに必要な筋肉が疲労します。
それが継続する為、疲労が貯まり、むくみと相まって血流が悪いため、症状がでやすくなっています。
③運動不足。
健康に欠かせないものとして、運動がありますが、それを定期的に行っている人は2~3割ほどしかいないのが現状です。
お客様に話を聞くと
「仕事で疲れているのに、仕事帰りに運動なんて!」
「その時間がない」
「運動が苦手、嫌い」
という理由があります。
肩こり腰痛予防の為には、できれば定期的に運動することが一番だと思いますが、このような方の健康をお手伝いする事が整体というお仕事です。
症状が辛くなる前にお越し頂ければ、早く良くなります。
我慢している期間が長いほど、コリが強くなる。
また、椎間板の変形や関節の変形まで起こることがあります。
我慢せずに整体を活用することを薦めます。
④個人の体質。
①個人の回復力は、体質や個人差があり、その能力値を判断するのはできません。
70歳すぎても回復力の高い人、若くても回復力の低い人もいます。
基本的に
・加齢による回復力低下。
・血液循環を低下させる要素。
が治癒力に影響します。
血液循環を低下させる要素
高血圧、肥満、筋力低下、臓器の機能低下は、血液循環に悪影響を与えます。
回復力とは何か
回復力(治癒能力)とは何か?
私、48歳、短距離走(100m)の11秒代に挑戦中。
※現在挑戦5年目、挑戦開始時は13秒3(公式記録)。現在12秒4(公式記録)※公式記録とは、陸連の許可がおりた大会でのタイム。
回復力の落ち込みは、20歳を超えると感じますが、30代半ばで小突かれ、40代前半で1発殴られるような感じでした。
タイムを更新するには、練習強度を上げたいのですが、上げすぎると故障します。
「子供の頃のようにすぐに治りたい!」
「回復力を上げたい!」
と思い、回復力について調べてみました。
意外ですが、現在の医療でも、
「それが何かははっきりしない」
という事がわかりました。
なので、現在、個人的にできることは、疲労抜きをして回復力に専念させるという意識をもって行動するしかないと思いました。
そして、疲労について調べました。
疲労については、コチラ(当院別サイト)で詳しく書いています。
個人の体質
個人の体質とは、
・回復力。
・骨格の形。
・筋肉の使われ方(関節の動かし方や筋バランス)もあります。
・臓器の能力。
・考え方(思考タイプ)。
骨格の形
骨格の形は、椎間板や軟骨の変形や骨自体の歪み、筋バランスの不良により骨格に歪みが生じます。
そして、先天性(生まれつき)の場合もあれば、後天性(生活習慣や事故による後遺症)の場合もあります。
椎間板や軟骨の変形例
・背骨のヘルニア
・椎間板損傷
・脊柱管狭窄
・半月板損傷
骨自体の変形例
・変形性関節症(頸椎、胸椎、腰椎、股、膝、足)
・骨盤の変形
・脛骨変形
・大腿骨変形
・脚の骨の長さの違い
その他
・骨盤の開きや歪み。
・髄核移動による椎間板の変形。
筋肉の使われ方
普段の生活や運動で使われる筋肉の比率は、個人個人違います。
先ほどの変形による影響とそれ以外に
・遺伝にる筋肉のつき方。
・親の体の動かし方を見て自然まねる。
・生活環境に合わせた体の使い方。
が考えられます。
例えば、歩く際に前進力を得る方法による違いでは
膝の屈伸による前進方法や股関節の屈伸による前進方法があります。
日頃、観察する限りでは日本人は膝の屈伸で進むことが多いです。
この場合、ハムストリングスという太ももの後ろにある筋肉が使われますが、この筋肉の起始部の影響で骨盤が後傾しがちになり、腰部の前弯が減少しがちです。
股関節の屈伸で進む場合は、膝の屈伸が少なく股関節の屈伸が強くなり、太ももの前にある四頭筋やお尻の殿筋が頻繁に使われます。
この場合は、四頭筋の起始部である骨盤を前傾させ、腰部の前傾がキープされやすいのが特徴です。
また通常、歩行時は爪先(足先)は進行方向を向くものですが、股、膝、足の関節や骨の変形があれば力が入りやすい動き異なり、歩く際に爪先が外や内を向くことがあります。
このように個人によって筋バランスは異なり、個人で使われる筋肉が違い、それが腰や肩への負担が増すと、そこに痛みが生じやすくなります。
膝の屈伸で見る筋肉バランス不良例
※関節に変形がないことが前提です。
鏡を正面にして立ちます。
その後、お尻と踵がつくように膝を曲げて腰をかがめます。
そして、膝を伸ばし立ち上がります。
この立ち上がる運動の際に筋バランスが悪いと膝が内側や外側に傾きます。
そうなる方は、膝関節の内か外に荷重か加わり、膝を傷めやすい傾向にあります。
このような影響から腰痛や肩コリの予防法は
・疲労回復
・全体的な筋トレや柔軟性の確保
・筋バランスの改善。
があります。
整体の役割は、これらを手技で改善させたり、アドバイスする事にあります。
臓器の能力
臓器は五臓六腑と言われ、それぞれの役目があります。
その臓器は、生まれもって弱かったり、生活習慣により機能が低下することがあります。
臓器の病や機能低下は、その臓器の症状以外にも関連痛として腰痛や肩コリ、気だるいなど症状も併発させます。
また、それが血液循環や質と関係する臓器であれば症状はでやすくなります。
病気に対しての整体の役割
整体を受ければ病気が必ずよくなるというものではありません。
病気に対しての整体の役割は、ストレスを減らして、体にある回復力をその病気に専念しやすくするだけです。
ストレスとは、精神的なストレスだけではなく、体への負担すべてをいいます。
ストレスについては、コチラで詳しく書いています。
臓器の機能低下による関連痛により腰痛や肩コリの症状であっても、整体ではそれを和らげることは可能です。
そして病気を回復方法は、改善に繋がることをできるだけ腐らず地道に行うしかありません。
また、病院から処方されるお薬、手術が必要であれば、早く決断することを薦めます。
⑤心理的要因
心理的要因は、コチラで詳しく書いています。
最後に
痛みの原因について、書くと長文になってしまいました。
原因は、このように多くのことが体にマイナスに働いて症状として表れる為、その原因を一つづつ改善していくことが大切ですが、もう一つの考えかたがります。
体にプラスになる事を加える。
体にいい事をするという方法です。
腰痛・肩こりがでるかでないかは、この足し引きでマイナスが多いとも言えます。
足し算、引き算についてはコチラで詳しく書いています。
整体は、体にプラスを加える方法になります。
当院でお手伝いできることは
・歪み、疲労、コリによる痛みの改善。
・痛みをなくす情報を差し上げること。
になりますが、当院を活用頂くことで生活がなって頂ければ嬉しく思います。