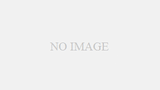心理的要因。
自力で腰痛や肩コリがなかなか改善できない場合、心理的要因が原因にある時もあります。
それは
・脳の仕組み。
・脳疲労。
の問題です。
脳の仕組み
私たちの脳には、ホメオスタシス(生体恒常性)という機能が備わっています。
.gif)
これは、体温や心拍などを一定に保とうとする機能です。
例えば、夏に暑くなると室内であればクーラーをつけることが多いと思います。
ですが、クーラーで体を冷やさなくても私たちの体温は、外気と関係なく一定のままです。
人間は、筋肉を震わせて体温を上げて平熱に保っています。
これが外気の温度に左右されて体温が下がると活動が制限されます。
トカゲなどの爬虫類は、この機能がないために外気の影響を受けてしまい、体が冷えていると動けなくなります。
また逆に暑さに対しては汗を皮膚から出して、それが蒸発し気化することで皮膚の熱を奪い体温が下げる仕組みになっています。
そして、心臓の鼓動も一定に保たれるようになっています。
運動をすると心拍は上がりますが、やめれば元に戻ります。
このように私たちの体の中にはバランスをとり一定に保つという恒常性機能(ホメオスタシス)が常に働いています。
このような機能が備わっている為に、現状の生活を変えたいと思い行動をしても、結局元の生活に戻ってしまうと考えられています。
500万年前から続いていた恐怖の世界
また、遺伝的な要因で脳はこのような変化を嫌う性質もあると言われています。
それは、魔女裁判にあるような変化に対しての排除です。
魔女裁判は、まわりと違ったり変わった事をすると、他者に密告されて処刑されるというものでした。
また、人類の期限は500万年前と言われており、原始的な生活を長い間続けています。
その時代は、さらに恐怖が身近にあったと思います。
外部からの侵略者や侵入者、普段見かけない人が突然襲ってきたかもしれません。
そして、洪水や台風などの急な気候変動に対しても無防備でした。
コンクリートの家なんてありません。
このような時代では、変化を見逃す事が命取りになります。
今の日本は治安が高いと言われていますが、そのような社会が成立したのは第二次世界大戦後以降です。
以前は日本刀をもった人が、そこら辺をウロチョロしています。

そして、無礼を働いた人に対して
「切捨御免」
と言って、切りつけてもよいという制度が江戸幕府の時代にはありました。
日本でも常日頃、恐怖を身近に感じる生活が昭和になる前まではありました。
つまり、治安のよい日本でさえもほぼ恐怖が身近にある生活が500万年も続いていたと言えます。
本能
このような500万年という経験が脳の大脳辺縁系には蓄積されています。
本能と言われている部分です。
動物の赤ちゃんは、本能的に誰に教わるでもなく生まれてすぐに立とうしますし、お乳を探しますよね。
そのような本能が人の脳にも備わっているため、周囲と違うことをすると攻撃対象にされるかもしれない。
危険だ!
と認識します。
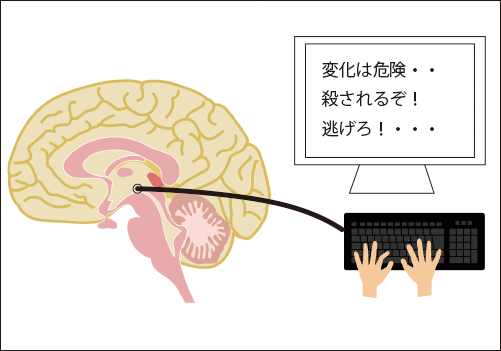
つまり、生活習慣の改善も普段違うことである為にアラームを出してしまい
「今日から運動するぞ!」
と考えても、本能に負けてしまうのです。
脳疲労
脳疲労とは、文字通り脳が疲れている状態です。
現代社会、やる事、覚えること、たくさんありすぎて脳は疲労傾向にあります。
また生活するために働かなくてはいけませんが、仕事以外にも立場によって育児や介護、料理、掃除、洗濯が加わります。
さらに、これらにストレス要素が加われば、さらに脳の余裕はなくなります。
脳の絶対的な役割は、生命維持です。

脳の負担が増大すれば、体に乱れが生じる事があります。
ストレスからおこる自律神経失調症は正にそれです。
それゆえに脳はストレスになることを避けようとします。
※ストレスは、精神的なものだけではなく、脳の負担になるもの全てを指します。
ストレスについては、コチラで書いています。
ストレスが増えて脳で処理することが膨大になると
「めんどうくさい」
と思って、活動させないようにしています。
このような現状があり
「姿勢を正そう」
「運動をしよう」
「食事を減らそう」
と思い、やり始めても
「今日は気分がのらないから辞めておこう」
「え~い、明日からがんばろう!」
「雨降ってるから・・・」
と脳がやらない為の理由を探しだします。
続かないのは、このような理由です。
だからといって何もやらないでは、何も変わりません。
もし今現在、症状があって放置すれば悪化していくかもしれません。
⑤心理的な問題
腰痛や肩コリに繋がる心理的な問題は、ストレスだけではありません。
以下の事が関係して痛みに繋がっている事もあります。
・不安症
・思い込み
・痛みの閾値が低い
心理的な問題ではこれらが関係して、腰痛や肩コリを感じやすくしています。
不安症
不安症とは、精神的な不安から、心と体に様々な不快な変化が起きる病気の総称です。
病気には、以下のものがあります。
・パニック障害
・社会不安障害(社会恐怖)
・強迫性障害
・全般性不安障害
各病気の症状は、上記のリンク先で書いてありましたので、ここでは省きます。
精神的不安が痛みに繋がる理由
精神的な不安から、腰痛や肩コリが起きる理由に脳の機能低下があります。
脳の機能といっても、脳全体の機能低下ではなく、痛みを抑制する為の機能が低下することがあります。
疼痛抑制機能
人間の脳には、鎮痛薬のような機能があります。
「これが強く働けば、痛い思いをしなくていいのに」
と考えてしまいますが、健康維持には痛みを感じない方が都合が悪いので、ほどほどにという事なのでしょう。
その鎮痛薬と似た役割をしているのが、脳の下降性疼痛抑制系というシステムです。
下降性疼痛抑制系とは、脳が痛みを感じた時に伝達物質としてセロトニン、ノルアドレナリンを分泌し、それが患部の神経に伝達して痛みを和らげる仕組みです。
詳しくは、コチラ(外部サイト:大川整形外科)に画像つきでわかりやすく書かれています。
また、脳の中にあるDLPFCの萎縮も関係することがわかっています。
DLPFCとは、脳の中にある背外側前頭前野と呼ばれる部分です。
このDLPFCの働きには、患部から伝わった脳の記憶を消す役割があります。
このDLPFCの機能低下が起こると、痛みの記憶を消すことができず、治っているのに痛みを感じるという事が起こってしまいます。
脳には、このような鎮痛薬のような機能がありますが、その働きが弱まる理由が、ストレスや不安感の長期化です。
つまり、脳が痛み止めを出さなくなるので、痛みを感じやすくなります。
病院の検査で異常なし。
痛みが辛く病院で検査してもらったのに、病院の先生から
「異常なし。」
と言われた。
「痛い!、なんで?」
というのは、このシステムの機能低下があるのかもしれません。
また、これは通院した病院の画像検査(MRI、X線)でわからかっただけかもしれません。
脳の機能は、凄い!と言われていますが、完璧ではありません。
体に侵入してきたものが毒でもないのに、それを毒と判断したり、過剰に反応するアレルギー反応はよくある病気です。
※整体では、病院では行わない矯正や徒手療法を行い、病院の見立ても違いますが、整体でもこのような機能低下が起こっているかどうかはわかりません。検査をお願いするのであれば、ペインクリニックの医師に相談するのがよいと思います。
〇治し方
・疲労を溜め込まない。
・負の感情をおこりにくくする事。
負の感情をおこりにくくするには、物事の捉え方を変える方法があります。
怒らないでお読みください。
パッと思いつくこととして、散歩中にウンコを踏んだら
「誰がここに糞を放置したんだ!」
と怒りMAXになりそうですが、「運」がついたかもしれません。
そう思うしかない。。。
宝くじを買いに行くことだけは、辞めた方がいいと思います。
もう少し品のよい例はと。
お腹いっぱいで食べる白米と1日絶食して食べる白米は、同じ白米でも満足感は異なります。
何かの出来事でおこる感情の違いは、同じ出来事でも捉え方で変わるものです。
年に数回、書いているきじポ~新聞ではこのような内容を主に書いています。
よろしければ、お読みください。
きじポ~新聞は、コチラ。
思い込み
思い込みという言い方だと、
「痛みがないのに痛がっている。」
という意味でとらわれそうですが、そういう意味ではありません。
過去にツライ痛みを経験したり、その話を聞いたことによって、痛みと関係する動作をする時に筋肉が無意識に働き痛みに繋がることがあります。
このような働きを防御性収縮と言います。
防御性収縮
防御性収縮とは、過去に強い痛みを経験し、その際の痛みが強くなった動作を怖がり、その動きを止めようと無意識で行ってしまう筋肉の反応(収縮)です。
この防御性収縮は、傷めた筋肉が働くような日常生活の動作に起こるようになり、それが解消されずに残ってしまうことがあります。
そして、この反応がある方は、反応が弱い人に比べて治りにくい傾向にあります。
その理由には、このような働きがあると痛みを訴えている患部の筋肉はさらに収縮したり、余分に疲労することにが原因です。
詳しくは、コチラで説明しています。
痛みの閾値が低い。
痛みの閾値とは、体に与える刺激を次第に強くしていき、「痛い」と感じる強さの事を言います。
この閾値が低い人は、痛みに対して敏感という表現になります。
そして、これは個人個人異なります。
痛みが敏感になる原因に、
・疲労が蓄積。
・負の感情(怒り、悲しみ等)が強い。など
があります。
つまり、この体質になっている場合、物事の捉え方や普段の生活での疲労蓄積があります。
これらは、腰痛や肩コリの原因ともいえ、これらを生活から減らす事が健康体質になるとも言えます。
痛みの閾値について、コチラで詳しく書いています。