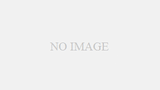呼吸法で腹圧を高めて腰痛・肩こりを緩和させる。
腰痛や肩コリの原因は、
「姿勢の悪さ」
がありますが、それだけではありません。
肩コリや腰痛の原因。
肩こりや腰痛の原因には
①筋肉疲労。
②骨格の歪み。
③ストレス。
④脳の誤作動。
⑤内臓疾患の関連痛
などがあります。
姿勢の悪さから影響を受けるものは①、②です。
ですが、その改善は生活環境を変える事が難しいことや、生活習慣を簡単に正せないことにより改善できない事が多いです。
しかし、少しづつでも改善しなければ加齢や運動不足による筋力低下に伴い、肩こりや腰痛の発生リスクが高まります。
今回は、横隔膜(腹式・腹圧)呼吸で①筋肉疲労と②骨のズレの緩和に繋がるのか説明します。
横隔膜呼吸で期待できること。
腹圧を高める横隔膜呼吸で腹圧が高まることで腰痛や肩コリが緩和されるのは、以下のことが理由にあります。
①筋肉疲労
②骨格の歪み。
①筋肉疲労
筋肉疲労というと肉体労働やスポーツで起こるものと思いがちです。
ですが、姿勢を維持する為に筋肉は働くため、寝る姿勢以外では働きっぱなしです。
その働きっぱなしの筋肉は、体幹を維持したり、腹圧を高める筋肉です。
その筋肉は、姿勢が悪いと無意識にそれを正そう働いてしまいます。
姿勢が悪いほど筋肉が使われることになり、筋肉疲労を起こしてしまい、それが腰痛や肩コリの根本的な原因となります。
②骨のズレ
背骨がズレる主な原因は、筋力低下と猫背などの姿勢不良にあります。
特に猫背になることで、背骨は後方にズレ、後方にズレるほど側弯や猫背が強くなる傾向にあります。
さきほど筋肉疲労で説明したように、脳は姿勢を正そうと筋肉に働きかけます。
慢性的な骨のズレ(サブラクセーション)があれば、意識して姿勢を正しても正すことが難しくなり、ズレが強いほど、筋肉疲労も大きくなります。
腹圧増加は、なぜよいのか?
腹圧増加が良いのは、この①筋肉疲労や②骨のズレを緩和させる働きがある為です。
一般的に「体を支えているのは骨だ」というイメージがあり、「骨がなければタコみたいになる」なんて言われたりします。
背骨(図1)を見たると上半身の重みは背骨が支えているように見えます。

確かに骨が支えていますが、姿勢を維持する筋肉でも支えています。
姿勢維持筋
ここでは、静止時の姿勢を維持する為の体幹の筋肉について説明します。
姿勢維持する筋肉は、体幹を前後左右に作用させる筋肉と腹圧を高める筋肉です。
市販の本によっては、背筋が大事とだけ書かれているものもありますが、実際はそうではありません。
背筋が大事だと言われるのは、図1の背骨を見た時に背骨が体幹の後方にある為、体が前に倒れるのを防ぐことができる筋肉が背筋の為、そう言われがちです。
ですが、実際に姿勢を維持するには体幹を前屈、後屈、左右の回旋、左右の側屈に働きかける筋肉と腹圧を高める筋肉が姿勢維持にかかわっています。
多くの筋肉がありますが、腰痛や肩コリを予防する上で重要になるのが腹圧を高める筋肉です。
腹圧を高める筋肉が重要な理由。
猫背になると頭の位置が体より前に位置します。
その頭の重さは個人差がだいぶあり、体重の8~10分の1ほどと言われています。
重さにすると4kg~8kg程と言われています。
猫背の姿勢だと体は前に倒れるような力が働きますが、そうならないように背中側の筋肉が働いて、それを阻止しています。
この時に背中側の筋肉の負担を分散させているのが腹圧です。
腹圧とは、腹腔(図2)にかかる圧力です。
.gif)
以下のページで腹圧について、詳しく説明しています。
腹腔への圧力(腹圧)を高めているもの。
腹圧は、筋肉(横隔膜や腹筋群、骨盤底筋)が働いて圧をかけています。
その圧力を高める要素に骨のブロックがありますが、前面だけ骨のブロックがありません。
骨による後方の補助は、背骨と肋骨。
側方は、肋骨と骨盤。
底面は、骨盤。
上面は、骨はないですが横隔膜があり、その横隔膜の上に肺や心臓があります。
前面は、腹直筋、内・外腹斜筋、腹横筋という筋肉だけがあります。
腹筋が大事な理由。
背骨は図1で説明したように体の後ろ側に位置しており、その為に頭や上半身の重みによって自然と腰からくの字に曲がりやすくなっています。
ですが、これは骨だけを見た場合です。
実際には、背骨の前には内臓が詰まった腹腔があります。
わかりやすく説明する為に、この腹腔を仮に風船とします。
この風船が、お腹の中にある事で上半身の体重を風船にあずけることができます。
風船が強ければよいのですが、風船は上半身の重みに耐えきれず、押しつぶれ体は前に倒れてしまいます。
つまり、風船がつぶれないによう働きかけているのが筋肉で特に腹筋が作用しています。
この腹筋の働きが強いほど姿勢が悪くても背筋の負担を分散でき、背筋にだけ疲労がかからない為、腰痛や肩コリが起きにくくなる理由です。
また、猫背になりにくくなる為、背骨の後方変位を抑える事もできます。
ただし、腹筋が強ければいいかという訳ではなく、常に腹圧を高めているかという問題もあります。
腹筋があっても、腹筋を緩めて背筋の負担の使用率が高ければ背筋に疲労がたまり、腰痛や肩コリは起きやすくなります。
腹筋は強いと思うけど、下っ腹がでている人はその傾向があります。
腹圧のエクササイズ
それを治すには意識していて正す方法があります。
意識の仕方は、意識して呼吸で行う方法と下っ腹に力を入れる方法があります。
腹圧を高めるエクササイズについては、過去2回書いています。
①横隔膜呼吸によるエクササイズコチラ。
②腹圧を高めるエクササイズはコチラ。
下っ腹に力を入れる方法は、意識して臍の下に力を入れるだけです。
ただ、それだと普段から下っ腹の筋肉が使えていない人は、力を入れきれないかもしれません。
その場合、右の拳を握って下っ腹に小指側の方を振り下ろします。
拳のナックルを当てると骨が当たるので、それは止めてください。
普通に痛いです。
下っ腹を固めきれて腹圧が高いと拳を跳ね返しますが、弱いと痛いです。
まずは、弱めに叩いてください。
それを何度も確認していると、下っ腹に力が入っている感覚がわかるようになります。