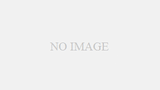痛みを感じやすい人と感じにくい人がいます。
それは、痛みの閾値(しきいち)と痛みの捉え方で影響を受けます。
※閾値については、コチラに書いています。
痛みの捉え方
「痛いのが好き」
という人が、稀にいるみたいですが、私も含めほとんどの人は、好きではないと思います。
そんな「痛み」を、強い痛みとして過去に経験すると、痛みを起こした際の動作に対して無意識に身体が反応することがあります。
整体の症例でいうと、ギックリ腰と四十・五十肩の人に多くみられます。
ギックリ腰は、地べたをはってしか移動することができないくらい、腰に激痛がでることがあります。
四十・五十肩の人は、腕を動かすだけで激痛を感じ、腕を上げれなくなることがあります。
このような激痛を感じると患部を保護するためか、無意識に患部周囲の筋肉は硬くなります。
また時間経過と共に症状が改善せずに慢性化すると、筋疲労が起こる為に動作時の痛みを増強させます。
また、稀ですが、
動作=痛い
と脳が記憶することがあり、どこも悪くないけど、痛みを感じるようになる事もあります。
要は、トラウマになってしまう訳です。
なので、この場合はトラウマを書き換える事ができれば、症状の改善に繋げることができます。
その方法に認知行動療法があります。
痛みは悪い?
確かに痛みは、嫌なことですが、
痛み=悪
ではありません。
痛みは、体に悪い事が起きているというシグナルです。
それがわからないと体が危険な状態に合っていることがわからずに命を落としやすくなります。
また、痛みを知らなければ、他人の痛みもわからない為に危害を与える恐れもあります。
その為に小さい頃から、「痛み=良くないもの」と教育されています。
これらは視点を変えれば、「痛み=良いもの」と捉えることができます。
・痛みのサインは身体に悪いことが起きている事を知り、悪化を防げます。
痛みは痛みでしかない。
また、痛みは痛みでしかありません。
痛み=悲しい・ツライというのは、教育で受けたものです。
私には2歳(2022年時)の娘がいますが、走るのが好きですが、よく転びます。
それを見た、妻は
「大丈夫?」、「痛くない?」
と声をかけていました。
このように声をかけることは、
痛み=よくないもの
と認識する為に、そういう言い方は止めさせています。
転んだ時には、ほおっておくか。
「みそら、強いね~」
※みそら:娘の名前。
と肯定的な言葉をかけるようにしています。
痛みに感謝する。
こう言うと怪しく感じ、抵抗を感じる人がいるかもしれません。
痛みは、脳があたなの為に良かれと思ってしている事と言いました。
その痛みに対して、それを嫌だなと思えば、体に良い事を否定することになります。
脳は、あなたの為に生命を長く維持する為にこのような事を起こしています。
それを否定する事は、体にとっていい事でしょうか?
誰かがあなたの為を思ってアドバイスした時にそれを否定すると、その人はあなたにアドバイスをしなくなります。
脳は、自分を生かすことが最優先にあるので、そういう事はしませんが、面白くないに決まっています。
試しに行ってほしいのですが、痛みを感じた時に心から自分自身に
「ありがとう」
「いつもありがとう」
「頑張ってくれてありがとう」
など、励ます言葉を言ってください。
声にした方がいいですが、出さなくてもいいです。
心の中で言うだけで効果があります。
体が軽くなるのを感じると思います。
施術中のできごと
お客様とこのような会話をした時に、腰痛で立つ事がツライ人がいて、その人がこれを続けていただけで痛みがなくなった人が身近にいたという話をしていました。
その人は、まだ本気で信じていないようでした。
そして、試しに施術中に「ありがとう」と声にだしてみたら?と提案して
お客様が「ありがとう」といった瞬間、硬くなっていた筋肉が緩みました。
簡単です。
思うだけでいいんです。
ポジティブに捉える。
病は気からという言葉があるように、心の状態は体に働きかけます。
思考は現実化するという言葉もあります。
例えば、喉がかわいて水筒に入っていた水を飲んで、半分残った状態の時。
「もう半分しかない」
「はだ半分もある」
捉え方で感情は変ります。
否定的な感情は、精神的ストレスとなり、体に悪さします。
思考の癖ですぐには治せないですが、否定的な思考をした時に後から肯定的な思考をすると、人は後者の思考を受け取ります。
否定的な思考をした場合は、肯定的な思考に変えてください。
その癖が痛みや辛さを和らげることに繋がります。
そういう風に育てていると、転んで擦り傷ができて血を見ても
「血が出た、痛い」
と、ぐずるくらいで泣きません。
このような心と身体について本に書かれていたので紹介します。
足を痛めたワンちゃんの話

愛犬のレトリバーが、雪が降ってきた事にはしゃぎすぎた為か足を痛めてしましました。
痛みの為に足を引きづりながら家の中に戻ってきて、暖炉の前でうずくまります。
それを見た、飼い主は大丈夫?
と寄り添いますが、その気苦労からか持病を悪化させてしまいます。
ですが、ワンちゃん、翌日には元気に走り周れるようになりました。
というお話。
動物は、痛みを感じはするものも、それがツライものだとは思わないようです。
かという人間は、心の状況が身体に影響を与えます。
「火事場のくそ力」、「病は気から」もそれを表した言葉です。
映画「ランボー」の2か3でも、怪我をして凹んでいるランボーに教官が
「痛みは痛みでしかない」
みたいな事を言っていました。
認知行動療法①=痛みは痛みでしかない。
痛くても、何もできない訳ではありません。
痛くても、できることがあります。
脳の反応を書き換える。
痛みが慢性化すると、脳が痛みを出す動きに対して痛みを感じるようになることがあります。
これを改善させるには、痛みを出しそうな動きをしても、身体が悪くならないことを覚えさせていきます。
例えば、ギックリ腰の経験者であれば、立位から座位、またはその逆で痛みを経験している方が多いのですが、その動きに対してぎこちなくなります。
座る時に腰を曲げすぎないようにしたり、立つときに腰に手を当てたりします。
また、何かの動きでギックリ腰が発症した人は、その動きを怖がります。
前者の場合であれば、立位や座位を繰り返す。
後者であれば、その動きと関連する運動から始めます。
これらを繰り返し行っても
階段は、1段登り、1下がる。
地味ですが、これらを繰り返し行っても
「何も起きない」
というのを脳に記憶させる事でトラウマを解除させます。